就活と教習所をダブルでこなして、わたしは疲れていた。
秋の日と言えども夏の名残の湿度と気温にまいって、くらくらする頭を手で庇いながら歩いていると、前方で通行人の流れが淀んでいることに気付く。
流れを遮っているのは、真島さんだった。真島さんが、女の子と歩いているのだ。
小顔で巨乳でヴィヴィアンの服を纏った女の子。
異様な、明らかに堅気ではない雰囲気と、ただでさえ長身で無駄に美形なので目立つから、行きかう人たちは大きく迂回して、真島さんを避けて通っている。
そのまま何食わぬ顔で、真島さんがわたしに気付いても素通りしてしまうか、あるいは更に大きく迂回して真島さんに気付かれないように帰るか。
考えているのもつかの間、真島さんの右目と目があった。
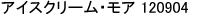
ジェラテリアの紙箱の中、ドライアイスの敷き詰められた中に、バニラとストロベリーのアイスクリームがふたつ。
揺らめく白い冷気に顔を撫でられて、いつもと当然のごとく同じお土産を前にため息をつく。
真島さんの訪問は今週で三度目なので、つまりいま手元に六つも、バニラとストロベリーがあるわけで。
わたしのアパートの冷凍庫なんて、型落ちした小さい代物であるから、ほうれん草やおもちや鶏肉の合間を縫ってぎゅうぎゅうに押し込まなければならない。
「うぅん……ぎりぎりいけるかな?」
ぶつぶつ言いながら在庫整理しているわたしなど意に介さず、真島さんがわたしのベッドの中に潜り込むのが見える。
「何時に起きる?」
「あぁ……起こさんでえぇ。おやすみ」
弱々しい声、いまにも眠りに落ちていく瞬間の彼の姿。
最近うちに来ることが多いということは、いま、彼女いないのかなあ。
でも、あのヴィヴィアンの女の子は……。
わたしがけさ目覚めて、また今夜眠るベッドに横たわる真島さん。
淡い色合いのシーツとカヴァーに包まる、見た目も中身も極彩色の彼との対比は、何百回見てもやっぱり変だ。
だめだ……一個どうしても入らない。諦めて、はみだしもののストロベリーを食べてしまうことにし、プラスティックのスプーンを手に、ベッドにもたれ掛ってカーペットに坐る。
ワンルームなので、別室という空間がないため、こうして彼が眠りに訪れたら、いつも静寂を保つのに気を遣う。
電気を消して、パソコンのモニタの照明をすこし弱くして……。
しかし、パソコンを前にすると、真島さんの存在もすっかり忘れて没頭することができる。
だから、卒論に追われているいまは、彼の訪問は大変ありがたいものだった。
彼は、眠っているときほんとに存在感ないし、音もたてないし、死んだみたいだ。起きているときは嫌っていうほど目に入ってくるのに、眠ったら電源ごとオフにしたみたいに思われる。
ワードを叩いたり、モニタを見ながらアイスクリームを食べたり、を繰り返して、疲れて首を回して。
ふと、時計を見ると、一時間ばかり経っていた。
後ろをそっと振り返る。
さっき横向いていた体が、いつのまにか仰向けになっていて、青白いなにかの中毒者のような顔に、モニタのぼんやりした光の帯が横切っている。顔だけは変わらず壁側へ背かれていて、その長い睫毛と頬、やや寄せられた眉根のカーブの向こう側は暗闇を重ねている。
自分のすぐそばで、眠っているひとがいるという状況は、なんとなくくすぐったく、快くもある。息を殺しているのも楽しく、それでいてときどき漏れてしまう自分から発せられる音にも、いたずら心をくすぐられる。
誰にでもこんなふうな気持になるのではあるまい。胸がじわりと温かくなる、この気持には。
またモニタに向かい合ってキーボードを叩いていると、肩の後ろから、ぬうっと手が突き出てきた。革手袋をした、冷たい手が。
「わぁ!」
その手がわたしの肩を掴んだので、心底びっくりして跳ね上がる。その瞬間まで、また真島さんの存在を忘れて没頭していたので。
「………いま……何時や」
疲れてくぐもった声。
振り返ると、わたしの肩を掴んだままの真島さんが、暗い顔で、上体を起こしているところだった。わたしはすぐにモニタの右下に表示された時計を見る。
「まだ二十二時半。真島さん、一時間半しか寝てないよ」
「そぉか、よぉ寝たわ」
いつも起き掛けは頭でも痛いみたくつらそうに見えるけど、きょうは特にそうだな、と思う。
またこの一時間半だけの睡眠で、三十時間くらいずっと起動しているのだろう。
「なんや、アイス食べとったんか」
パソコンわきに置き去りにされた、からっぽのアイスクリームの容器。
目ざとくそれに気づいて、真島さんが「の大好物やもんなぁ?」としたり顔で囁くのを、わたしはちょっと白けつつ聞いている。
“アイス言うたらバニラかイチゴや”という彼の独断によってはじめは手土産に持ってきていたそれが、いつのまにか彼の中で“バニラかイチゴのアイス言うたらの大好物や”に変わっていたらしい。
十年間、毎度毎度与え続けられているわたしが辟易しているとは、彼は微塵も思うまい。
いいや、思っているかもしれない、気づいていたとしても、“ま、喜びよるやろ”の一言で、またバニラとストロベリーを買ってくるのだ。
「、水くれや」
「うん、ちょっとまって」
立ち上がって、ワンルームのため短い距離の先にある冷蔵庫に向かう。わたしがいつも使っている安物のコップに入れた水を、真島さんは三口ほど飲みこんだ。
「もうちょっといれるの?ここに」
「あぁ。まだ時間は問題ないな」
「家帰るの?」
「事務所行く。おまえの兄貴と冴島とで会議せなならん」
「え、兄と冴島さんっていま中国でしょ?あ、テレビ電話的な?」
「あぁ。」
おまえの兄貴のふざけたツラ見なならんのは気ィ進まんわ……とぼやく真島さんにわたしは頬笑んで、ベッドに坐る彼の足元の床に坐った。
……突然の沈黙を感じる。
真島さんがわたしの部屋のベッドに仮眠を取りにくることは日常生活の一部になるほどよくあることだが、彼は、寝て起きればすぐにいつも出ていってしまう。
だから、こうして、ベッドのふちに腰かけて、わたしの部屋の壁をぼんやり眺めているこのひとに対して、どう反応すればいいのかわたしにはわからなかった。
まえは、こんな沈黙なんて、ちっとも気にならなかった。彼の前でくつろぎ、のびのびと過ごしていたし、寝転がって漫画を読んだりだらしなくすることもできた。
いまでは、あんなことができていたのが、遠い昔の出来事のようだ。
真島さんは何にも変わっていないのに。
「そういやおまえ」
「ん?」
「きょう何しとったんや?泰平通りおったやろ」
「あ、うん」
わざとそこには触れないようにしていたから、どきっとしたし、すこし傷ついた。
ヴィヴィアンの女の子と一緒にいた真島さん。
真島さんからしたらわたしに女の子とデートしているのを見られても、なんともない、僅かにもまずいと思ったりされない、その当然すぎる事実が、わたしはやっぱり、ちょっとだけ、わかってたけどショックだった。
「教習所行ってたの」
「ほぉ。いまどこやねん」
「えっとねぇ、こんど高速乗る」
「せいぜい死なんようにな」
「うん。……」
「免許とれたらドライブ行くで!助手席でハンドルさばき検定したる」
「ええ〜……静かに乗っててくれるならいいけどさ〜」
口を噤んで、その傍らにいた女の子の影を必死に思い浮かべないようにしているけれど、くるくると巻いた黒髪や、洋服の柄なんかが、ちらちらと脳裏に焼き付いていて、ふとしたときに見えてしまいそうになる。
こんなことで悩んで、ばかみたいだ。いいや、ほんとにばかなのだろう。
わたしが真島さんの身辺の女のひとのことで考えたって、なんにもできないのに。
仮にわたしが文句を言ったって、真島さんは当然怪訝な顔をするだけだろう。
わたしなんて、部下の妹でちょっと世話してくれてるだけなんだから。
「で、就活はどやねん。いけそうか?」
「うーん……あんまり思わしくないね。」
「アホ、もっとガッツガツいけや!」
「わたしにやれることはやってるもん。不況が悪いのよこの不況が」
「かァー、一丁、俺流の就活方法伝授したろかい」
「バット振り回すとかそういうのならいい。」
「ヒッヒッヒッ」
意地悪く笑う真島さんが、ごろりと床に寝転がって、わたしの膝におもむろに頭を載せる。
どきっとして体がすくむけれど、真島さんがこんなことをするのに他意なんてもちろんない。
膝に重みを感じながら、わたしの顔の真下にある真島さんの顔を見る。横向きになったその顔は、気持よさそうにくつろいでいて、目を閉じて、なんだか子どもみたいで。
こぼれて触れる髪の感触とか、首筋とか、そういう重さや質感の触れるところ以外でも、わたしの体はなんだかざわざわして、おかしくなったみたいだった。
膝枕なんて、真島さんはしょっちゅうしてくるけど。わたしが子どものときから。
でも、最近はあんまりなかった。だから、いま、ちょっとやばい。
「ま、頑張ってんのやったらええわ。大学も卒業出来んねやろなァ?」
「う、うん。まあ。なんとか。」
「選り好みせんとどこでもええから受けてこいや。受かったとこからがどこで働くか決めたらええねんから」
「わかってるよ……もう」
「有名どころしか受けてへんのやろ。あ?急がんと内定あらへんで卒業なるで。暗い袴なんて着とうないやろ!」
「へーい……」
膝枕しながら親みたいなこと言われてもね!と思うけれど、その発言はやっぱり体に響く。
わたしが一番焦ってるんだから。
どこでもいいともまだ割り切れてないけど。
でも就活のことに関しては、真島さんが帰ってからじっくり考えてみるとして。
いまはどうしても、意識が膝の上に傾いてしまう。
髪の毛きれいだな、とか、しょりしょりしたうなじがすごくくすぐったいな、とか。じっと見つめてみたいし、頭や顔に触れたいな、とも思うけれど、どれも、わたしには許されていないことだ。
あのヴィヴィアンの女の子なら、それができるのだろう。
膝に触れる感触は同じはずなのに。
「……あかん。寝てまいそうになった」
「寝れば?」
「いやもう事務所行くわ」
がばっと起きて、おもむろに立ち上がった真島さんの後に残された感触を名残惜しみながら、わたしも立ち上がる。
さきに電気をつけに真島さんを追い越して玄関に向かうと、お尻をパァンと叩かれて体が強張った。
「いった〜!なによ!」
「いやァちっちゃい尻やから叩いてデカくしたろ思てな。そないしょーもないケツしとっから就職決まらんのや」
「ばぁぁっかじゃないの!?」
「怒んなや短気やのー。ケツの穴まで小さいんかいな」
「最低すぎるね。もーはやく行きなよ」
「おう、言われんでも行くで。ほなまたな」
「うん、またね……」
立ったまま靴を履く背中を見つめる。突然その背中に触れてみたら、このひとはどんな顔をするのだろうか。“なんやねん”と不機嫌そうに言うのだろうか。
扉を押し開けて、頭をやや屈めて出て行く彼が、一度わたしに振り向いた。
その目に“好き”と伝えたらどうなるのだろう。“子供のころからずっと”………とても言えない、言えるわけがない。
関係が壊れるのがこわいから。
“またな”と挨拶してくれたその言葉が、無くなってしまうのがこわいから。
ぱたんと閉まった扉を見ながら、アイスクリームだらけの冷凍庫を思い出して、ため息が出た。
 |